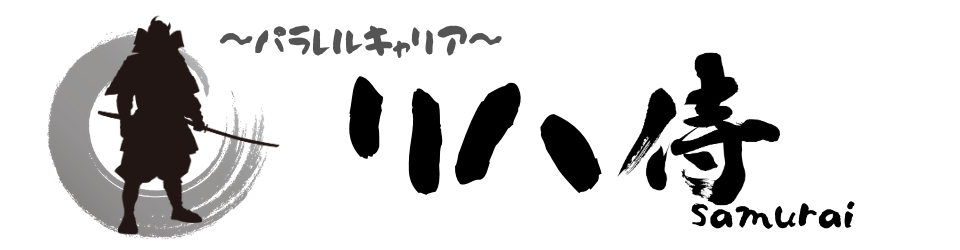大腿周径は測る位置によって、内側広筋や外側広筋など筋肉の状態を知ることができます。
周径の誤差や左右差の診方、大腿四頭筋の各筋肉の評価方法をご紹介します。
周径は特に膝疾患の患者さんに対し、重要な評価項目の一つです。
正確な周径の測定法や測定位置をしっかりと抑え行いましょう。
周径の測定方法とは…

周径はメジャーを用いて計測します。
メジャーは100円均一でも簡単に準備ができます。
計測時に3つのポイントに注意することで、正確に計測することができます。
それでは次の3つのポイントを抑えましょう。
〜3つのポイントとは〜
①メジャーがねじれていないこと
②大腿部に対しメジャーを垂直にあてる
③巻いたら一度軽く引っ張ってから緩める
周径のポイント①
一つ目はメジャーがねじれていないことです。
大腿の裏側でねじれていることがあり、ねじれると長さが変化してしまうため注意しましょう。
周径のポイント②
二つ目は、大腿部に対しメジャーを垂直にして計測をすることです。
メジャーを斜めに置いてしまうと周径の長さが変わってしまい、正しく計測できません。
大腿部に対し垂直に合わせ計測をしましょう。
周径のポイント③
三つ目は、一度軽く引っ張ってから緩め計測することです。
計測時に引っ張ってしまうと、実際より細い結果となってしまいます。
正確に測るには、メジャーを巻いた後に一度軽く引っ張ってから緩めます。
こうすることで、メジャーが隙間なく大腿部に接するため正確に測定することができます。
この3つのポイントを意識し、周径を行いましょう。
各筋肉の周径位置とは…
大腿部の周径位置によって、計測のポイントとなる筋肉が変わってきます。
〜大腿部の計測位置〜
膝蓋骨 直上 ⇒ 炎症の評価
膝蓋骨 5㎝上 ⇒ 内側広筋
膝蓋骨10㎝上 ⇒ 外側広筋
膝蓋骨15㎝上 ⇒ 大腿部全体
このように測定位置を変えることで、ポイントとなる筋肉が変わってきます。
特にTKA(人工膝関節全置換術)やACL損傷(前十字靱帯損傷)などの膝疾患の方には、様々な位置で計測し大腿部の評価を細かくしましょう。
誤差や左右差、考え方とは…
周径を実施した際にどのくらいが誤差か迷うと思います。
0.5㎝であれば誤差と捉えてよいでしょう。
周径の差が1㎝以上生じている場合は、誤差ではなく差があると捉えてよいです。
筋肉の量を比べる場合は、左右差で比較します。
これに対し炎症症状を比較する場合は、前日の同側の周径と比較します。
炎症症状を左右差で比べると、前日と比べどのくらい悪化しているのかわかりずらいです。
そのため炎症症状を評価するときは、毎日同側の周径を測り検討する必要があります。
まとめ
今回は大腿部の周径についてご紹介してきました。
大腿部の位置によって周径結果の意味合いが変わってきます。
みなさんも各位置で評価し、しっかりと大腿部の状態を把握しましょうね。
特集
勝ち組 理学療法士になるには、ストロングポイントと理学療法を融合させることが重要です。