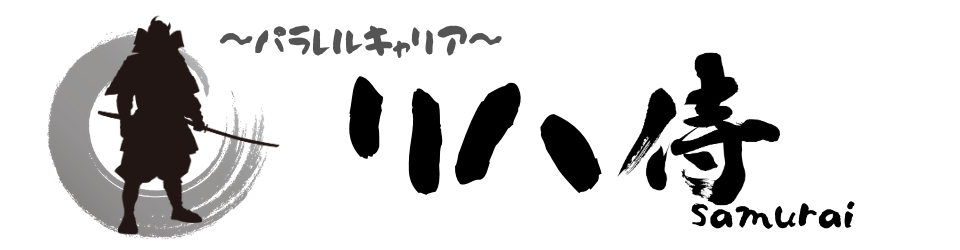Warning: Undefined array key 4 in /home/suketomaru/pt-rinshou.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 21
Warning: Undefined array key 4 in /home/suketomaru/pt-rinshou.com/public_html/wp-content/themes/sango-theme-poripu/library/functions/prp_content.php on line 33
歩行観察で3つのポイントを行うことで、実習や症例検討のレポートが書きやすくなります。
少しでも歩行観察が苦手だと思う学生や若手セラピストは要チェックです。
リハビリをするうえで、歩行観察は必須ですよね。
しかし学生さんや若手セラピストの中には、同じ場所に立ちジーっとみているだけで歩行観察をしている方もいます。
このような歩行観察をしている方に限って、レポートで歩行観察を書くときになかなかうまく書けませんよね。
今回ご紹介する歩行観察のポイントをおさえるだけで、レポートで歩行観察を書くのが楽になります。
やりがちな間違った歩行観察とは?

歩行観察は必ず行いますが、うまく書けていますか。
し学生や若手セラピストの中には、間違った歩行観察をしている方もいます。
次の項目に当てはまる方は要注意です。
〜要チェック〜
□一方向からしか観察していない(前額面だけなど)
□動作の観察だけして触診をしていない
□イメージで歩行観察をしている。
歩行観察のポイントとは?
歩行観察で必ず行うべきポイントは次の3つです。
〜歩行観察のポイント〜
◆前額面、矢状面から観察
◆触診をする
◆身体部位をモニタリングする
前額面・矢状面から観察
ずっと同じ方向から歩行観察をしていませんか。
歩行観察は必ず前額面と矢状面の両方から行いましょう。
一方向からの観察だけでは得られない情報が多くあります。
〜ポイント〜
前額面 ⇒ 側方の動きの評価
矢状面 ⇒ 前後の動きの評価
前額面では側方への動きを見ることはできますが、前後の動きの評価は難しいですよね。
なかには前額面から歩行観察し前後の動きをイメージする方もいると思いますが、これはあくまでイメージであり評価ではありません。
評価は必ず見て、触って、事実をとらえることがポイントです。
例えば、前額面から歩行観察した場合、トレンデレンブルグやデュシェンヌといった跛行の評価は容易にできます。
では股関節の伸展の動きや、膝の伸展の動きはどうでしょうか。
これは矢状面からしっかりと評価しないとわかりづらい部分です。
前額面からみて股関節や膝関節の伸展の動きはでてそうに見えても、矢状面から観察してみると思ったより伸展していなかったって場合もあります。
このように一方向からでは得られない情報もあるため、必ず前額面と矢状面から観察をしましょう。
前額面と矢状面の動きを評価し、この2つを統合して水平面の動きがイメージできるとさらにいいですね。
触診をする
歩行観察をする際に、しっかりと筋肉も触診していますか。
歩行を見るだけで終わっている方は、しっかりと筋肉を触診し筋収縮を確認することがポイントです。
歩行観察だけして中殿筋の収縮が弱いと言う方もいますが、それはただの仮説にすぎません。
触診して初めて仮説から事実へ変わります。
歩行をみればどこを過剰に使っていて、どこが弱いのかイメージすることはできますが、そこで終わらず実際に歩行中に筋肉を触診し確かめることが重要ですね。
仮説で止まってしまうと想像での治療になってしまいます。
やはり見て、触って、確かめることがとても重要となります。
身体部位をモニタリングする
歩行に限らず動作を評価する際に、しっかりと身体部位をモニタリングしていますか。
例えば、歩行時に患者さんの骨盤に手を軽く置きモニタリングします。
歩行観察で視覚的に得た情報に加え、実際に患者さんに触れることでさらに細かい反応や情報を得られます。
視覚からの評価だけでは得られないことも多くあるため、触診やモニタリングは必ず行いましょう。
モニタリングや触診を行う上で、一つ注意する点があります。
それは患者さんの動きを阻害しないことです。
触るとうことは患者さんへ感覚の入力が入ります。
患者さんの本来の動きの情報を得たいので、極力患者さんの動きを阻害しないように評価しましょう。
教科書に当てはめていませんか
学生さんの中には、教科書に書いてあるような歩行観察をする方がいます。
しかし、実際の患者さんは教科書通りではありません。
学生さんに二人の片麻痺の方の歩行観察をさせると、両方とも同じ歩容を書くことがあります。
片麻痺の方の歩行パターンは似ている部分もありますが、個々で特徴や違う部分は必ずあります。
その特徴をみれていないと教科書と同じ歩容を書いたり、みんな同じ歩容になってしまいます。
重要なのは、『片麻痺の歩行=このような歩行』という固定観念を持たないことです。
要は自分の中で片麻痺の歩容を決めつけないということです。
患者さんの特徴を知るためには、ただ観察するのではなく、多方向から観察し、実際に患者さんに触れ評価しましょう。
そのためにも、さきほどご紹介した3つの方法を行いましょうね。
まとめ
今回は歩行観察のポイントについてご紹介しました。
学生さんの中には同じ場所から歩行を観察しているだけの方がいます。
しかしこれだけでは、歩行観察は不十分です。
より歩行観察の精度をあげ、しっかりと歩行観察をするためには、今回ご紹介した3つのポイントを抑えましょうね。